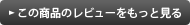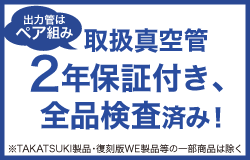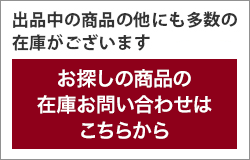お客様の声






- ホワイトストーン 様
- 投稿日:2024年06月14日
ゼネラルトランス販売さんからお借りしたトランス型ATT(FM-ATVR1×2)に使用されていました。上級L-Pad型ATT以上の素晴らしい音場感(定位)がしましたので、早速同じ線を使って製作することにしました。少し細いかとも思いましたが、34接点ですので、引き回しを考えて、Φ0.4mmにしました。






- UTP 様
- 投稿日:2024年06月07日
見かけにひかれて音のことは何も考えず購入しました。
ちょっと個人的に落込み気味だったので、これ置いたらカツが入るかなと思ったのかもしれません。
自宅のDKで主に和洋のpopsかける予定で購入しましたが、
ボーカルなかなかいいですね。オンマイクに聞こえます。
ピアノどうだろうか鳴らしてみたら、
10畳くらいの練習室的だったCDが公会堂のホール的に聞こえます。
不思議です。
無理は承知でディスコ音楽かけてみたら、
さすがに苦しい…当り前ですが。
1つ不思議なのは、正面のロゴが右下に来るように置く(通常と思います)と、
リアパネルのロゴが2台のうち1台は正立しますが
もう1台は反時計90度回転します(笑)
ま、音に影響があるとは思えず配置上も困らないのでそのままにしておきます。






- hiro 様
- 投稿日:2024年05月09日
今後、VT52シングルアンプを製作する予定なので、予備球の為に今回購入しました。
迅速な対応で気持ちのいい買い物が出来ました。






- やふきち 様
- 投稿日:2024年04月11日
EAR869プリメインアンプのプリ管として購入しました。オリジナルはEiエリート。そこからシーメンスに換え、テレフンケンとなる訳ですが、馬力やグルーブ感では前の2ブランドが上。しかし雑味のないしっとりした歌いっぷりではテレフンケンです。細かい音の表情をよく捉え、解像度も高いので、弦、ピアノ、ボーカルなど何を聴いても引き込まれてしまいます。新品に近くまだエージングが出来ていないので、これからがさらに楽しみです。






- 昭和音出し爺 様
- 投稿日:2024年04月05日
想像してたより作りがしっかりしていて、重量もありました。バナナプラグが使えるので自作スピーカー用としてこの製品を選びました。3台のアンプ、3セットの自作スピーカーを切り換えながら音出ししています。バナナプラグはベストな使い方ではないけれど、クリヤスクワランの助けも借りていい結果を得ています。







- Zig 様
- 投稿日:2024年03月23日
TU-8550を組み立てる際、どうしても横向きに真空管が挿入できず、試しにスクワランをピンに塗布してみました。綿棒にほんの少し付けただけなのにピンにすっと馴染み、全ての真空管が無事に挿入出来ました。非常に実用的な商品だと思います。






- 1954コード進行 様
- 投稿日:2024年03月20日
TRIODE TRV-A300の純正真空管の交換です
今年で70才 交換して良かったーー
レコード聴くのが楽しいーー
残りの人生が楽しいーー






- 1954コード進行 様
- 投稿日:2024年03月20日
TRIODE TRV-A300の純正真空管の交換です
今年で70才 交換して良かったーー
レコード聴くのが楽しいーー
残りの人生が楽しいーー